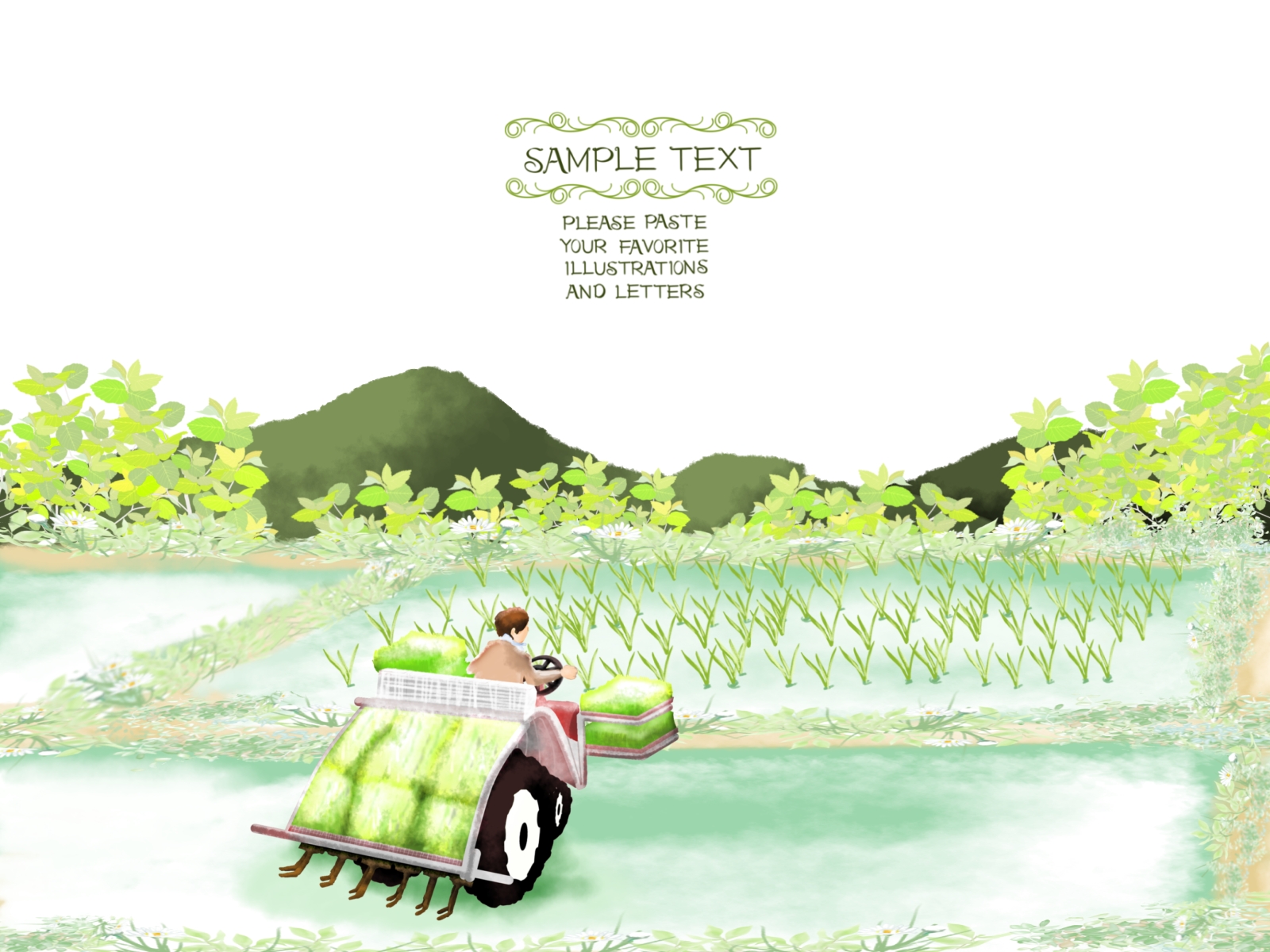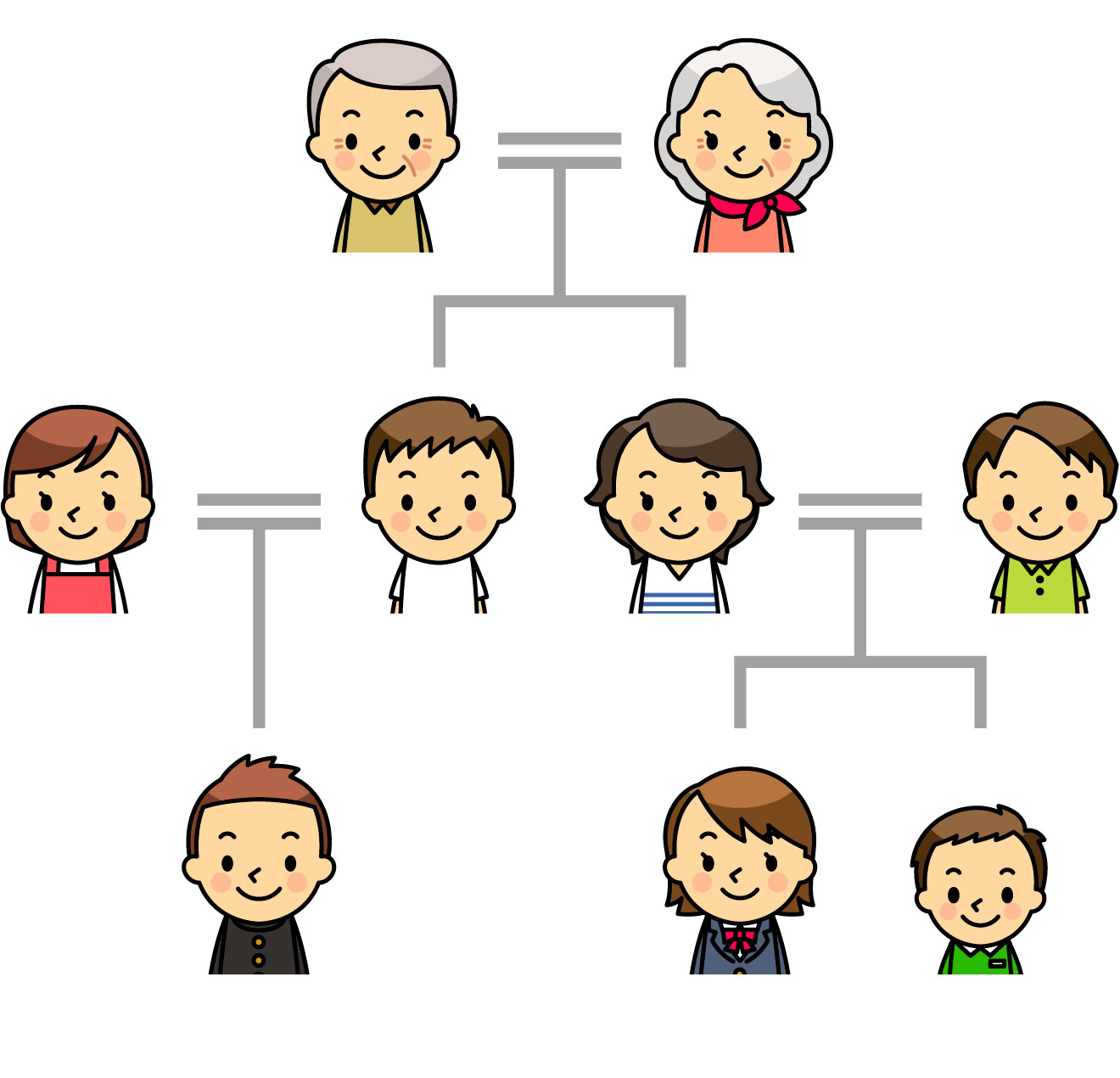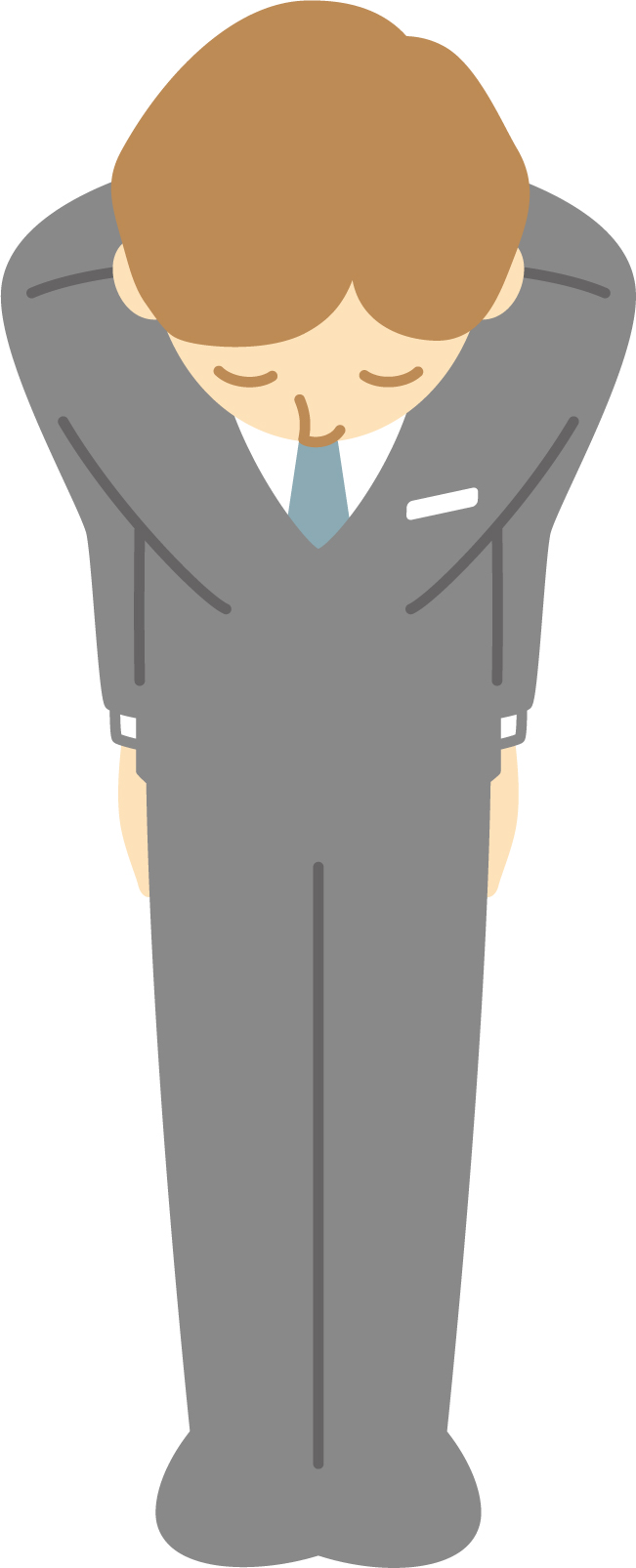農地の種類と農地法の許可基準
農地の種類
農地法許可の基準
◆農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地であり、原則として許可されません。転用許可を得る為には、まず「農振除外申請」をする必要があります。
◆甲種農地
市街化調整区域内農地で、集団的に存在している(概ね10ha以上)農地で高性能機械による営農に適した農地や、特定土地改良事業等の施行後8年以内の農地。 原則として許可されませんが、下記の様な場合は例外的に許可される可能性はあります。
・農業用施設や農産物加工施設、土地収用認定施設になる場合
・集落接続の住宅になる場合(敷地面積500㎡以内) 等。
但し、下記の第1種農地より厳しく審査されます。
◆第1種農地
10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地であり、 原則として許可されませんが、甲種農地の例外事例や次の様な場合は許可されることがあります。
・国道や県道の沿道のガソリンスタンドやドライブイン等沿道サービス施設やトラックターミナル、倉庫等流通業務施設になる場合等
◆第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地であり、 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可されます。
◆第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地であり、 原則として許可されます。
マイナンバーカード申請代行手続料「無料」期間が2023年2月末をもって終了致します。
総務省より
マイナンバー申請手続き料「無料」の期間が
2023年2月末日をもって終了すると連絡がありました。
但し、総務省の指示により途中で急に終了となる場合があるとのことです。
従って、申請手続き代行をお考えの方は、お早めにお申し込みください。
<お申込み方法>
次のいずれかの方法でお申込みください(受付順に手続きを致します)。
※申込人数多数の場合は、途中で打ち切りとなります。ご了承ください。
※所定の「委任状」をお渡しし、ご記入いただくことになります。
①お電話:079-495-3254 行政書士野原周一事務所までお電話ください。
「マイナンバーカード申請代行手続をお願いします」とご依頼ください。
その折・お名前・生年月日・ご連絡先・ご住所(兵庫県内にお住まいの方)をお尋ねします。
②メールによる場合
info@nohara-office.com までへメールをご送信ください。
その際、次の4点を必ず記載ください(いずれか記載の欠けているものは無効)
・依頼者ご本人様のお名前(ふりがな)
・ご連絡先(携帯電話が望ましい)
・ご住所(兵庫県内にお住まいの方)
・生年月日
※ご返信した場合を「受付完了」とさせていただきます。
現在は、遺言・相続(地域外も可)・車庫証明・マイナンバーカード手続代行業務のみ受け付けております! 現在は、遺言・相続手続き依頼が急増しています。
遺言・相続は、できるだけ手続を早く開始しないと、気が付いた頃に、手遅れになってい
ることが多いです。
遺言・相続は内容によっては、複雑になることが多いのも特徴です。
◆遺言
・遺言者の思いだけで、受遺者を決めれます。
・何回でも、書き直しができます
(公正証書にする場合は、費用が発生します)
◆相続
・遺産分割協議で「もめる」ことが多いです。
・相続税は、基本、死亡時より10ヶ月が期限です。
◆相続登記は2024年4月に義務化されますが、早めに
済ませましょう!(司法書士専権事項)